synthesis

入門
入門 / 日本語と英語で書いてあります

「糖」をキーワードとしてライブラリー合成をしようとする時、どのようなアプローチが試みられてきたかをカテゴリーに分類してまとめてみました。少し古いですが、参考にしてください。
金光さん→昭和大薬:薬化学教室(伊藤研)

「糖」関連の酵素、例えば、糖加水分解酵素や糖転移酵素の阻害剤は細胞の機能探索において重要な位置をしめています。例えば、ツニカマイシンはタンパク質にアスパラギン結合型の糖鎖付与する転移酵素を阻害しますので、糖タンパク質における糖鎖の「意義」を確認する実験をおこなうときに使われています。また、デオキシノジリマイシンなどは糖尿病薬としても使用されていて、この類の分子には将来いろいろな応用が期待されます。従来、天然物として単離され構造が決められたものが多いのですが、最近は反応機構の予測から論理的に設計、あるいは、タンパク質の結晶構造を基に設計してその後合成し阻害能の検定を行う手法が行われています。このような研究の流れをまとめましたので参考にしてください。
湯浅先生との共著です:東工大生命理工:湯浅研

イラスト:Shin

Synthetic Inhibitors of Proteins



ガングリオシドの1種GM3を少し修飾し、ポリグルタミン酸にペンダントのように導入しました。導入量が約1%と非常に低いにも関わらず、極めて強力にインフルエンザウイルスによる赤血球凝集を阻止しました。ヘマグルチニンを阻害する物質中でおそらく最強です。
上高原さん→京都大学大学院 農学研究科



以下の論文は、インフルエンザウイルスの表面にある2種類のタンパク質を同時に阻害しようとする「デュアルファンクション」の阻害物質の合成と評価に関するものです。仮に1/100000の確立で薬剤耐性株が出現したとすると2つ阻害すると、うまく行けばこの2乗の確立となるので、耐性株の出現を押さえ込むことができると考えられます。
孫さん→Cleveland State University

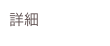

次は、アザ糖の中でも5員環のそれに注目した論文です。Chi-Huey Wong先生とともに理研のときから研究をしてきました。論文発表後に天然物として単離されたものや、極めて強力な酵素(グリコシダーゼ)阻害剤も含まれています。N-アセチルグルコサミニダーゼとN-アセチルガラクトサミニダーゼに対する阻害剤は、それぞれ世界最強です!!!
カルバ糖とも呼ばれるシクリトールの合成も行いました。設計は、イミダゾール環とシクリトールをスピロ体として結合したのですが、設計ミスからほとんど効果を発揮しませんでした。しかし、中間体のアミノシクリトールはかなり効いています。スピロ化合物は遷移状態アナログとなる様に5+5でしたが、シクリトールの配座の制御が困難です。5+6の基底状態アナログは機能性と考えています。
早乙女さん→京都大学大学院 医学研究科
中原くん→旭化成

Alpha-Galactosyl Ceramideの合成と免疫賦活効果

島村さんとの共同で一連の糖脂質を合成しまし、評価しました。ある種のNKT細胞に特異的な免疫賦活物質を見いだしました。
岡本さん→中外製薬

糖鎖合成における方法論に関する研究



左カラムの同じアイコンから専門サイトに解説しました。
小川先生、伊藤先生と研究していました:理研 伊藤研
赤穂さん→アステラス製薬


A new catalyst for the hydrogenation! A stable nanoparticle of Palldium(0) is very much stronger catalyst than ordinary Pd/C, and it works for solid-phase synthesis.
We confirmed this particle is stable for more than 10 years as a solution.
Gijis is doing good at Dept Microbiol. National Univ. Singapore

A non-destructive method of quantitative monitoring of solid-phase synthesis. A set of stable isotopes were used to monitor the reaction course where one is used as "a stationary beacon".
 Kanemitsu, T. et al. Angew. Chem. Int. Ed., 1998, 38, 3415-3418.
Kanemitsu, T. et al. Angew. Chem. Int. Ed., 1998, 38, 3415-3418.
 Kanemitsu, T. et al. J. Am. Chem. Soc, 2002, 124, 3591-3599.
Kanemitsu, T. et al. J. Am. Chem. Soc, 2002, 124, 3591-3599.
 Kanemitsu, T. et al. J. Carbohydr. Chem., 2006, 25, 361-376.
Kanemitsu, T. et al. J. Carbohydr. Chem., 2006, 25, 361-376.


A most challenging chemistry, synthesis of a combinatorial oligosaccharide library.
大塚さん→九州保健福祉大学 薬学部
マンゴーワインをありがとう! とても美味しかった 東京で売れます
鈴木さん、加藤さん→それぞれ特許事務所
続報執筆中!
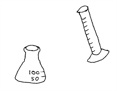




合成の部屋

解説
どうして馬跳びなのかが分かります


News

Chem. Asian J. の表紙 に採用されました
研究室の立ち上げ時からなんとかやらなくてはならないと思って少しずつ必要な合成ユニットの合成から始め、5年越しでようやくライブラリー合成が可能となりました。
この絵は、糖鎖のコンビナトリアル合成の概念を東洋的な感じに描いてみました。
野依先生が肝いりで立ち上げようとしていると聞き、是非投稿しようとインパクトファクターの無いnew journalに投稿してみました。しかし、三年経ったらChem. Eur. J.に肩を並べるくらいになってほっとしています。

「どんどん広がってほしいなあ」というのは感想ですが、カップリング反応に関するオルトゴナルケミストリーの生みの親になることができました。
メリフィールドは「オルトゴナル保護」の概念をだしました。とは言え、当初、そのようには彼らは言っておらず、保護基の独立性について説明をしたわけです。
1994年に我々の論文がJACSに速報として掲載された時点からにわかにこの「オルトゴナル」の言葉が世界中で使われるようになりました。(特許事務所からの問い合わせとかもありました)理由はよく分かりませんが「はっ」としたのでしょう。論文発表直後にオルトゴナル保護法の論文が出たのを覚えています。確かJACSでしたが、概念的には古いものです。保護基の話は「つぶし」のようにも感じていました。なぜなら全く新しい話ではないので、今更云々ではないと思っていたからです。また、学会では間違ったことを説明しておいて「私がルールだ」と言ってはばからない重鎮すら現れて困り果てました。(けんかになりそうになったことも。止めてくださった先生ありがとうございました。)
しかし、ありがたいことに、2年後にはデンドリマー合成の分野に飛び火し、その後、ポリマーやポリカテキンの合成へと広がっています。(祝!)そんな中で、“Interesting and provocative”, “One of the most intelligent methods”, “A paradigm” 等と称され照れますが誇らしく思っています。ヨーロッパでは大学院の教科書のチャプターにもなっていますし、多くの総説や書籍に引用されています。
最近気になることは、ペプチド合成(タンパク合成に近づいてきましたが)のある一派がネイティブライゲーションの同義語(概念的に同じ方法)がたくさんあるのでこれを、オルトゴナルカップリングと定めてはどうかという提案をしていること。これは、オルトゴナルカップリングではなく、ケモセレクティブカップリングですね。提唱者がどうもメリフィールド先生のお弟子さんというのも分からないではないですが引っかかります。
1996年にデンドリマーでオルトゴナルカップリングについて報告したチンマーマン先生の2013年のChem. Commun.の総説はよくまとまっています。
Orthogonality in organic, polymer, and supramolecular chemistry: from Merrifield to click chemistry
See you at
US Patent 7288565 - Azasugar compound